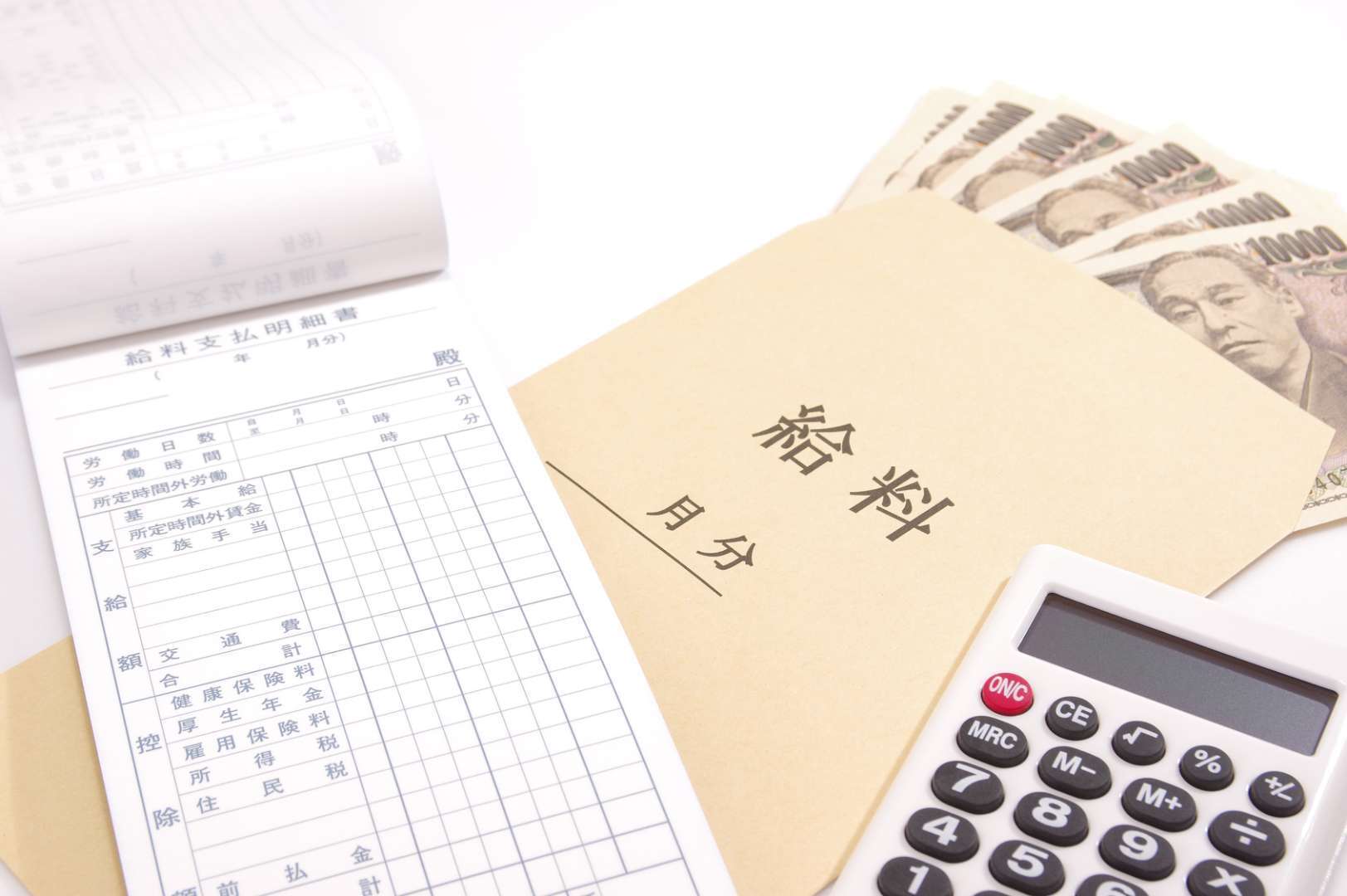「鳶職は稼げるって聞くけど、本当のところはどうなんだろう?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。高所作業という危険を伴う仕事であることから、「給料が高いのでは?」というイメージがある一方で、収入の実態が見えづらいのも事実です。
鳶職の年収は、働く地域や雇用形態、所属する会社の規模や受注案件の安定性など、さまざまな条件によって変わってきます。さらに、経験年数や保有資格の有無が大きな差を生むこともあります。
現場での役割や仕事の成果が収入に直結しやすい反面、不安定さを感じる人もいるかもしれません。だからこそ、正確な情報をもとに、自分に合った働き方を考えることが重要です。
本記事では、鳶職の年収事情を多角的に捉えながら、安定的に収入を得るための考え方や、将来的なキャリアの選択肢についても触れていきます。収入面に不安や関心を持つ方にとって、現実的な判断材料となることを目指しています。
全国平均と実態のギャップとは?最新データで見る年収相場
鳶職の年収を考えるうえで、まず押さえておきたいのは「全国平均」と「実態」との間にあるギャップです。厚生労働省の統計によれば、とび職人の平均年収はおよそ400万円台後半とされています。ただし、この数値はあくまで平均であり、実際の現場では個人差が非常に大きくなります。
たとえば、都市部の大規模な現場で働く熟練の職人であれば、年収600万円〜700万円に達するケースも珍しくありません。一方で、経験の浅い若手や、地方での小規模な現場に従事する場合は、年収300万円台にとどまることもあります。
また、給与体系にも注目が必要です。鳶職は日給制が一般的ですが、月給制や出来高制を採用する企業も存在します。日給制では働いた分だけ稼げる一方、天候や現場の状況に左右されるため、月によって収入に差が出やすい傾向があります。
加えて、雇用形態も年収に影響します。正社員として安定的に雇用されている場合と、個人事業主や一人親方として請負契約で働いている場合では、収入の仕組みそのものが異なります。手取り額だけでなく、保険や福利厚生の有無も含めて考えることが必要です。
このように、鳶職の年収は単純に「高い・低い」とは言い切れず、さまざまな要因が絡み合っています。次のセクションでは、どうすれば収入を伸ばせるのか、そのポイントに迫ります。
キャリアを積めば収入もアップ?昇給のポイントを解説
鳶職の年収は、ただ経験を積むだけで自動的に上がるものではありません。しかし、一定のステップを意識して取り組むことで、収入アップの可能性は確実に広がっていきます。
まず重要なのが、資格の取得です。たとえば「足場の組立等作業主任者」や「とび技能士」などの資格は、現場での責任あるポジションを担うために不可欠です。これらを保有していることで、任される仕事の幅が広がり、それに伴って手当や基本給が増えるケースも多く見られます。
次に注目すべきは、現場での役割です。単なる作業員から、チームをまとめる「職長」や、元請との調整を担う「現場責任者」へとステップアップしていくことで、収入面にも明確な変化が表れます。特に人手不足が深刻化している今、若くしてリーダー的なポジションを目指すことは現実的な選択肢となっています。
さらに、会社によっては能力に応じた評価制度を整えている場合もあります。たとえば株式会社フタバのように、技術力だけでなくチームワークや安全意識も評価軸に含めて昇給を行う企業では、努力が形になる仕組みが機能しています。
こうしたポイントを意識しながらキャリアを積み重ねていけば、単なる「作業者」から一段上の立場へと進むことが可能になります。収入を上げたいという思いを持つのであれば、長期的な視点でのキャリア設計が欠かせません。
鳶職の「収入の波」を生む3つの原因
収入を安定して得たいと考える方にとって、鳶職の「稼げるけれど不安定」という印象は気になるところかもしれません。実際、年収が一定しない背景には、いくつかの構造的な要因があります。
第一に影響するのが「天候と季節」です。鳶職は屋外での作業が中心となるため、雨や雪、台風などによって作業が中止になることがあります。特に梅雨や冬場は工期が調整されることもあり、働ける日数が減ることで月収に直結します。
第二に、「現場の有無」による収入の変動があります。常に案件があるとは限らず、次の現場との間に空白期間が生じると、その間の収入はゼロになるケースもあります。これは特にフリーランスや一人親方に多く見られる傾向です。
第三に、「ケガや体調不良」が仕事に大きく影響します。高所作業は常に身体的なリスクを伴うため、一度のケガが長期離脱に繋がることもあります。休業補償があるかどうかは雇用形態によって異なり、正社員であっても制度が整っていない企業では不安定さを感じやすくなります。
こうした不安定要素が重なることで、「月によっては思ったより稼げない」「将来的な収入が読めない」といった不安につながりやすくなります。だからこそ、次のセクションでは、こうした波をどう乗り越えていくのか、安定した収入を実現するための働き方について掘り下げていきます。
安定した高収入を得るには?会社選びとキャリア設計の視点
鳶職として収入を安定させるには、個人の努力とともに、どのような環境で働くかが非常に重要です。特に近年は、ただ現場に出るだけでなく、長期的に安心して働ける職場環境を選ぶことが、結果として高収入につながるケースが増えています。
まず着目したいのが「安定受注のある企業かどうか」です。元請けから継続して仕事を請けている会社や、公共事業・大規模開発などの案件を多く持つ企業では、季節や景気に左右されにくい基盤があります。これにより、現場間の空白期間を減らし、年間を通して安定した収入を得やすくなります。
次に、「社員育成や安全管理が徹底されているか」も見逃せません。たとえば株式会社フタバでは、社員教育や安全指導を重視し、働く側が安心してスキルを伸ばせる体制が整っています。こうした環境では、資格取得や役職昇格に向けた支援も受けやすく、自分の成長が給与に反映される機会も自然と増えます。
さらに、評価制度の透明性や福利厚生の充実度も、安定収入の鍵となります。たとえば交通費支給や社会保険の完備、有給取得の奨励など、細かな制度が生活の安定に大きく寄与します。
このように、「どの会社で」「どんな働き方をするか」は、鳶職の年収に直結します。単に給与額だけでなく、その金額が安定して続くかどうか、未来の自分を支える環境かどうかを見極めることが大切です。
興味のある方は、実際に企業の採用ページや現場見学などを通じて、職場の雰囲気を自分の目で確かめてみるのも一つの方法です。
▶︎ 採用情報はこちら
鳶職の年収は「選び方」と「積み重ね方」で決まる
鳶職という仕事は、単に「稼げるかどうか」で語られるものではありません。確かに高い収入を得る可能性はありますが、それは偶然ではなく、自分の努力と環境の選び方によって築かれていくものです。
年収の高さだけでなく、その安定性、将来性、自分らしい働き方を実現できるかどうかを見つめ直すことで、鳶職としての可能性は大きく広がります。特に、会社の取り組みや育成制度、安全管理の体制などをしっかりと確認し、自分に合った職場を選ぶことが、長く安心して働くための第一歩となります。
「手に職をつけて稼ぎたい」と考える方にとって、鳶職はその想いを実現できる職業の一つです。ただし、目の前の給料だけに目を向けるのではなく、その先に続く道や、日々の積み重ねが生む価値にこそ注目してみてください。
もし、働く環境やキャリアの考え方についてもっと知りたいという方は、会社説明や問い合わせを通じて、直接情報を得ることも可能です。
▶︎ お問い合わせはこちら