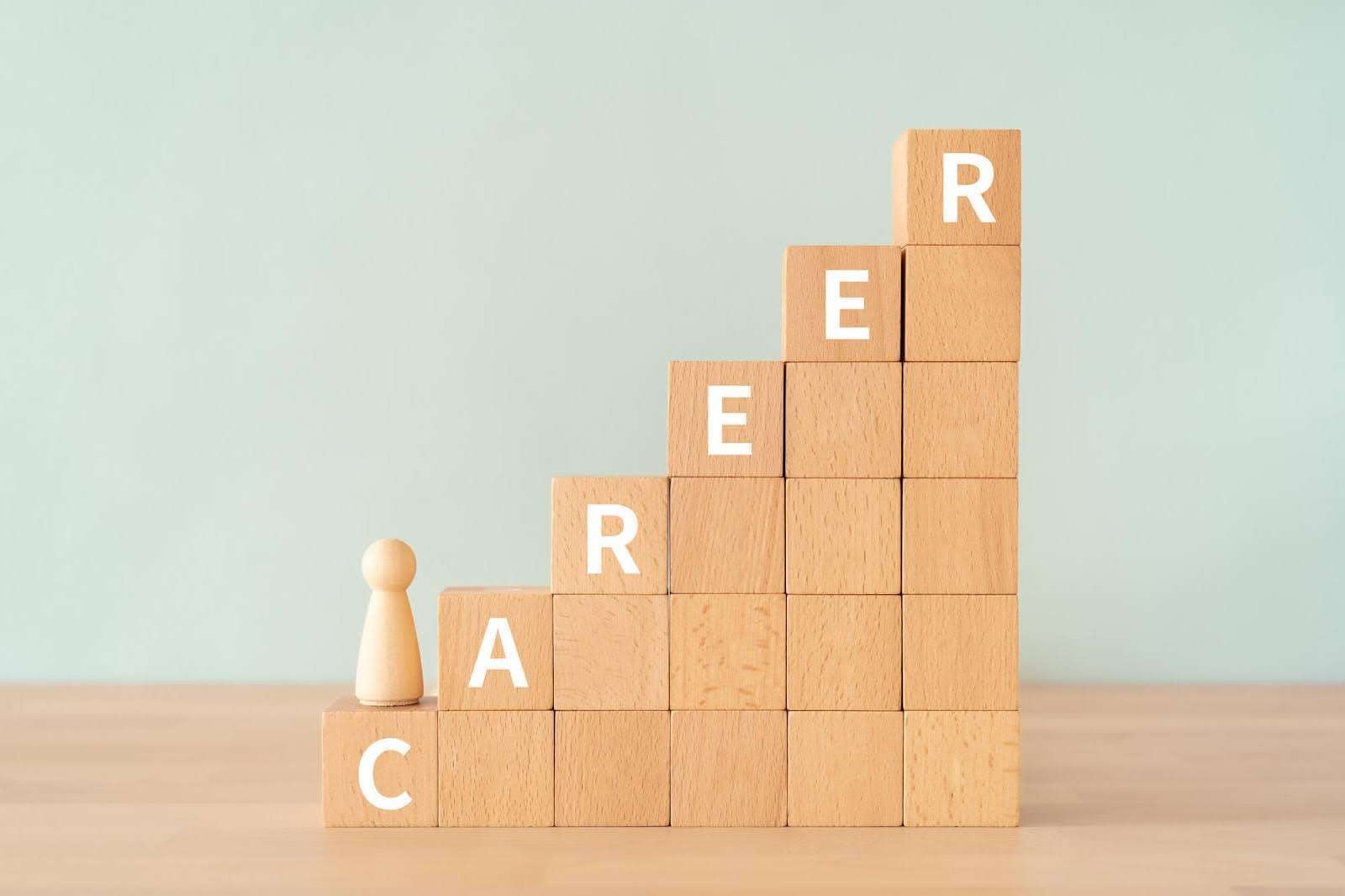「鳶って、ずっと現場で働き続けるしかないの?」
そう感じている方は、決して少なくありません。鳶職は体を使って現場で作業するイメージが強く、年齢を重ねるほど体力的に厳しくなることを想像しがちです。実際、若いうちは稼げても将来的に不安を感じるという声も聞かれます。
また、「資格がないとキャリアは築けないのでは?」「リーダーになれる人は一部だけなのでは?」といった疑問を持つ方もいるかもしれません。たしかに、鳶職は他の業種に比べて、キャリアパスが見えづらい部分があるのは事実です。
しかし近年、鳶職の働き方や役割は大きく変わりつつあります。安全性や品質がより重視される中で、現場をマネジメントできる人材へのニーズが高まり、経験やスキルを活かした新たなキャリアの形が広がっています。
このセクションでは、「鳶職にキャリアはあるのか?」という疑問に対し、現場の実情や変化を踏まえながら、将来を見据えた働き方のヒントをお伝えしていきます。
見習いから職長、現場管理まで。鳶職の成長ルートとは
鳶職にも明確なキャリアの段階があります。最初は見習いからスタートして基本的な作業を覚え、少しずつ経験を積みながら責任あるポジションへと進んでいくのが一般的な流れです。体力勝負の仕事に見えるかもしれませんが、実は技術・判断力・信頼がものをいう、長期的な成長が可能な職種です。
まず、新人として現場に入り、道具の使い方や基本的な作業手順を覚える段階を経て、数年後には一人前の職人として足場の組立や解体を任されるようになります。ここで安定的に仕事をこなせるようになることが、最初のステップアップです。
その後、経験を重ねていくと「職長」と呼ばれる役割を担うチャンスが生まれます。職長は、現場での作業指示や安全管理、進捗の確認などを担当するリーダー的な存在です。作業だけでなく、人を動かす力やコミュニケーション能力も求められるポジションであり、収入面にも明確な反映があります。
さらに実務経験を積んだ後には、「施工管理」や「現場監督」といったポジションへキャリアを広げる人もいます。これらの職種では、作業そのものよりも現場全体の進行管理や顧客との調整、書類作成などが中心となります。体力に依存せず、経験を活かした知的な業務への転換が可能です。
このように、鳶職は単なる肉体労働ではなく、キャリアを積み重ねることで「人をまとめ、現場を動かす存在」へと進化できる職種です。自分の得意分野や志向に合わせて、多様なステージが用意されているとも言えるでしょう。
この資格がキャリアの分岐点に?鳶職に必要なスキルセット
鳶職としてキャリアを築くうえで、避けて通れないのが「資格の取得」です。資格は単なる証明ではなく、現場での信頼や仕事の幅、昇進・昇給にも大きく関わってきます。
代表的な資格のひとつが「足場の組立等作業主任者」です。この資格を取得することで、現場において足場作業の責任者としての業務を担うことができるようになります。多くの現場で必須とされる資格であり、取得しているか否かが仕事の内容や立場に直結します。
また、「とび技能士(1級・2級)」も重要な資格です。これは国が認定する技能検定で、技術力の証明として業界内でも評価が高く、特に1級を取得すれば、職長や教育係としての信頼を得やすくなります。さらに、公共工事などの入札に関わる場合にも、この資格の保有が有利に働くことがあります。
そのほか、「玉掛け」や「高所作業車運転者」「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」など、安全性に関わる資格も必要です。これらは、作業範囲を広げるだけでなく、自分自身と仲間の命を守る知識としても重要な意味を持ちます。
資格を取得することは、自分のスキルを可視化し、会社や現場からの信頼を得る近道でもあります。実際に、資格手当や昇給の条件としてこれらの資格取得を明示している企業も増えています。
また、こうした資格取得を支援する制度があるかどうかも、職場選びの大切なポイントです。たとえば研修費用の補助や、実技練習のサポート体制が整っていれば、挑戦しやすく、結果としてキャリアアップの道がひらけます。
鳶職として一歩先の役割を担いたいなら、まずは目の前の資格取得から。それが、未来への確かな一歩となります。
現場だけじゃない。鳶経験者のその後の選択肢とは
鳶職として経験を積んだ先に、どんな道があるのか。それは「現場で一生働き続ける」だけにとどまりません。近年では、現場経験を土台にした多様なキャリアパスが広がっており、自分の適性やライフスタイルに合わせて、選べる道は確実に増えています。
たとえば、施工管理職へのステップアップがあります。これは、実際の作業に携わるのではなく、工事全体の工程や安全管理を行う仕事です。現場を知っている鳶職人がこの職種に移行すると、作業員との信頼関係を築きやすく、現場全体の質を高める存在として期待されます。
また、建設業界の中で営業職や人材育成に関わる道もあります。新しい現場を獲得するために、企業と施工側の橋渡し役となる営業職は、現場経験を背景に提案力を持てる貴重な人材です。さらに、若手職人を指導・育成する立場になることで、自分がこれまで培ってきた経験を、次の世代に活かすこともできます。
独立・開業を目指す道もあります。一人親方として活動を始める人や、少人数の施工チームを率いる事業主として活躍する人もいます。もちろん責任やリスクも伴いますが、自由度の高い働き方や、経営者としての成長を望む人にとっては、大きなやりがいがあります。
このように、鳶職は「現場だけで完結する仕事」ではなく、「経験を活かして広がる仕事」でもあるのです。視野を広げてみると、キャリアの選択肢は意外なほど多様で、未来は自分の意志と行動次第で形作ることができます。
育成体制がキャリアを左右する。企業選びの視点とは
キャリアの可能性は、個人の努力だけで決まるものではありません。どんな職場に身を置くか、どんな人と働くかによって、成長スピードも将来の選択肢も大きく変わってきます。だからこそ、企業選びは鳶職人生において非常に重要な判断です。
まず注目したいのは、育成に力を入れている企業かどうか。先輩が付きっきりで教えてくれるOJT体制が整っているか、定期的な研修や安全講習が実施されているか、段階的にステップアップできる仕組みがあるかなど、具体的な教育制度の有無がポイントになります。
また、資格取得を積極的に支援してくれる会社かどうかも重要です。たとえば、受験費用の補助、講習への参加時間の確保、合格後の昇給や手当の支給など、制度として整備されていれば、自分の成長に専念しやすくなります。
さらに、キャリアの出口が明示されているかどうかも確認したい点です。現場作業員として終わるのではなく、職長や現場管理者、施工管理職といった将来的なキャリアパスを示してくれる企業では、自分の進む道が見えやすく、目標を持って働くことができます。
たとえば株式会社フタバでは、社員の成長に合わせて、段階的にスキルと責任の範囲を広げられる評価制度が整っています。現場での活躍だけでなく、マネジメント力やチームづくりといったソフトスキルも評価対象となるため、多面的に成長したい方にとって魅力的な環境です。
「キャリアアップしたいけど、どうすればいいかわからない」と感じる方は、まずどんな環境で育てられるかを知ることから始めてみてください。
▶︎ 採用情報はこちら
「鳶職=一生の仕事」になるために必要なこと
鳶職は、一見すると短期的な働き方に見えるかもしれません。けれど実際には、技術を磨き、経験を積み、正しい環境で育っていけば、一生続けていける仕事にもなり得ます。大切なのは、自分の未来に目を向けることです。
この仕事で長く活躍していくためには、目の前の作業に追われるだけでなく、「次に何を目指すか」「何を学ぶか」を自分なりに考え続ける姿勢が欠かせません。そしてそれを支えてくれる職場を選ぶことが、将来の自分をつくる第一歩になります。
鳶職にもキャリアがあり、成長の道があります。それは「高所作業のプロ」としてだけでなく、「人を育てる存在」「現場を支える管理者」としての可能性でもあります。あなたの積み重ねてきた時間と努力には、必ず価値があるのです。
もし、「もっと長く働きたい」「将来のことを真剣に考えたい」と思われた方は、まずは自分に合った環境を探してみてください。必要なのは、大きな一歩ではなく、小さな気づきから始めることかもしれません。
▶︎ お問い合わせはこちら